少し古い記事になってしまいましたが、4月9日(土)の朝日新聞朝刊に「特別科学教育」のことが紹介されていました。
「太平洋戦争末期、戦争に勝つには科学技術力の向上が必要と、国が進めた英才教育があった」のをご存知でしたか?今日は、これを取り上げます。
・成績優秀な子どもを選抜し、数学や理科のハイレベルな授業を受けさせた。
・1945年1月、東京、金沢、広島の各高等師範学校と東京女子高等師範学校の計4校で「特別科学教育」は始まり、5月からは京都第一中学にも広げられた。
・終戦後は目的を「世界平和に寄与すべき科学文化を創造すべき」に変えられたが、48年3月までに打ち切られた。
★「科学教育関係」資料から(金沢大学資料館保存)
・金沢では「特別科学教育班」と呼んだ。
・児童生徒は北陸各県の中学1~4年生と、国民学校4~6年生から校長が選んだ。
・1クラスは15人ほどで高等師範学校の教員らが教壇に立った。
・開始当初の45年1~3月のカリキュラムは全360時間。理数系の教科で全体の5割以上を占めた。数学63時間、物象(物理)54時間、生物36時間、工作36時間。
・国語は27時間と比較的少なく、音楽や図工などはゼロ。
★藤井裕久さん(元財務相、89)の話
・最初の特別講義で、日本の原子核物理学の父と言われた仁科芳雄博士から「君たちは新型兵器をつくる先兵だ」と言われたことが忘れられない。
・45年8月広島と長崎に原子爆弾が落とされたことを知り、「新型兵器とはこのことだったのか」とがくぜんとした。
・「米国は完成させていたのに、日本は中学生に科学教育を受けさせていた。腹が立ち、情けなかった」
・「英才教育は悪とは思わないが、時の政権が利用する危険性は常にある。歴史の教訓にしてほしい」
★ギフテッド教育
・文科省は昨年6月、得意な才能のある子どもの教育について有識者を集めて議論を始めた。
・米国で行われている「ギフテッド教育」を例に才能教育の方法も紹介されたが、「特別科学教育」のように、才能のある子を選抜して特別プログラムを与える英才教育には否定的な意見が相次いだ。
・昨年末には、国による英才教育は「子どもにラベル付けすることになりかねない」と懸念する考えを表明。
・一方、才能がありながら対人関係がうまくいかず、不登校やいじめの対象になる子がいるとして、その困難を解消する方法について議論することとした。
・今後は、才能のある子を誰が、どう見いだし、何を支援するかの具体策を検討していく必要だ。
選抜することより、実際に才能のある子はいるのですから、その才能をどう伸ばしてあげるかですね。
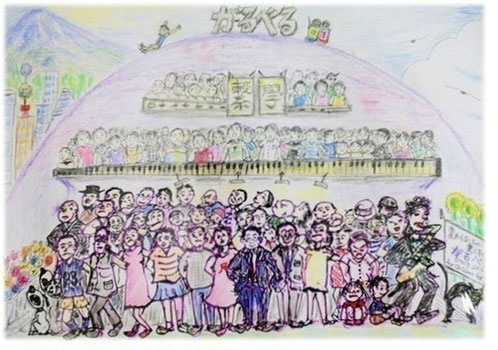
コメントをお書きください